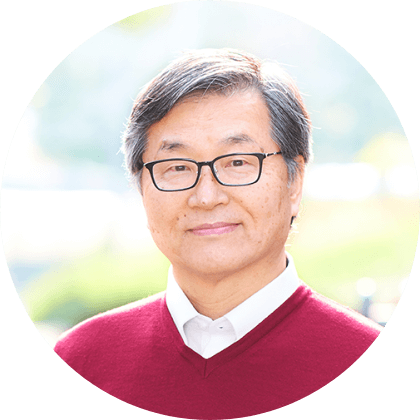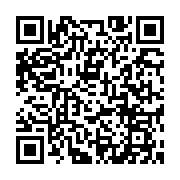過食症の子どもについては、「親のお金を盗む」という理解できない行動にでることがあります。しかしこれも食べたくてたまらない衝動がなせる技であることが多いのです。頭ごなしに叱らずに、理解の気持ちをもって、話し合えるといいですね。
1)「あら、私の貯金箱、どこへいったのかしら?美穂知らない?」
「500円玉が手に入ったら貯金をする」と決めていたお母さんがいました。赤いポストの貯金箱で、「ずいぶんたまったなー。いくらぐらいあるかな。楽しみだわ」と、手にとってはその重さがうれしくて。ところがある日そのポストが見あたりません。「あれ、どこへ行ったのかしら!?どこかに置き忘れたのかな」と、思いながら忙しさに探すのを後回しにしていました。
「美穂ちゃん、おかあさんのポスト知らない?500円玉貯金してたでしょ、あれよ」「えー、そんなもん、知らないよ」「えー、知らないってことないでしょ。あの赤いポストのよ」「知らないったら知らないよ!」。
こんなやり取りがあってしばらくして、今度はお父さんから声があがりました。「おーい、母さん、俺の背広の内ポケットから、お金ちょいどりしなかったか?」「なーに、人聞きの悪いこといわないでよ。ちょいどりですって?そんなことするわけないでしょ」。
2)さわがず落ち着いて状況を見極めましょう
過食症の子どもを持つ家庭では、「お金がなくなる」ということがときどきあります。そんな大きな額のお金ではないのですが、ちょこちょこあると親としてほっておけません。でも大声をあげて犯人さがしをするのは、すこし待ちましょう。
過食症の子どもが、食べたくてたまらずつい親のお金にてを付けるということがあります。食欲にスイッチが入ってしまって、食べたくてたまらなくなるともう理性ははたらきません。食べ物を求めて家中あちこち探しまわります。食べる物がなかったら買いに走ってでも食欲を満たそうと必死です。そのとき買うお金がなかったらどうする?我慢することができず、目についた貯金箱や背広のポケットのお金に手がのびることもあるのです。
3)ピンチをチャンスに・・・過食症の費用について話し合うチャンス
「うちの子がお金をぬすんだりするなんて」と、母親の嘆きをなんどか聞いたことがあります。しかし過食症の子どもの気持ちもしっかりと聞いてあげましょう。親子で過食症について本音で話し合う良い機会だととらえて。
落ち着いて問うていくと、子どもも観念したように話しだすことがよくあります。「食べたくて食べたくて、がまんできなかったの」と、涙をこぼしながら正直に話す子もいます。そんなときは「そうか、つらかったんやね。わかったよ」と、理解を示す言葉をかけてあげましょう。落ち着いて話しかけてもらうと、子どもはたいていポツポツとでも本音を話しだすことがよくあります。親のお金に手をだすほどまで、過食症の衝動が迫ってきていることに気がついてあげましょう。過食の費用としていくらか別に渡す必要があるのか、お小遣いの値上げですむのか。親子で過食症について、本音で話し合う機会がやってきたととらえて、落ち着いて話し合うことが大切です。
しかし中には親が甘い顔をすると、どんどんエスカレートする子どももいます。そんなときには、ピシッ!と叱らないといけない時もあります。
それでも良い対策がとれない場合は、摂食障害の専門家に相談しましょう。しろうと判断で取り組んでいると、症状がこじれていく恐れがあります。専門家を交えた何らかの対策が必要です。常識や正論でかたづけようとしても、症状は良くなりません。摂食障害の専門家に相談しながら、一番いい手だてをみつけていくことが症状がこじれない秘訣です。