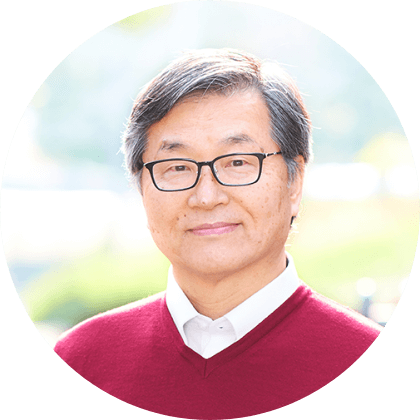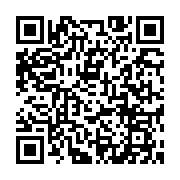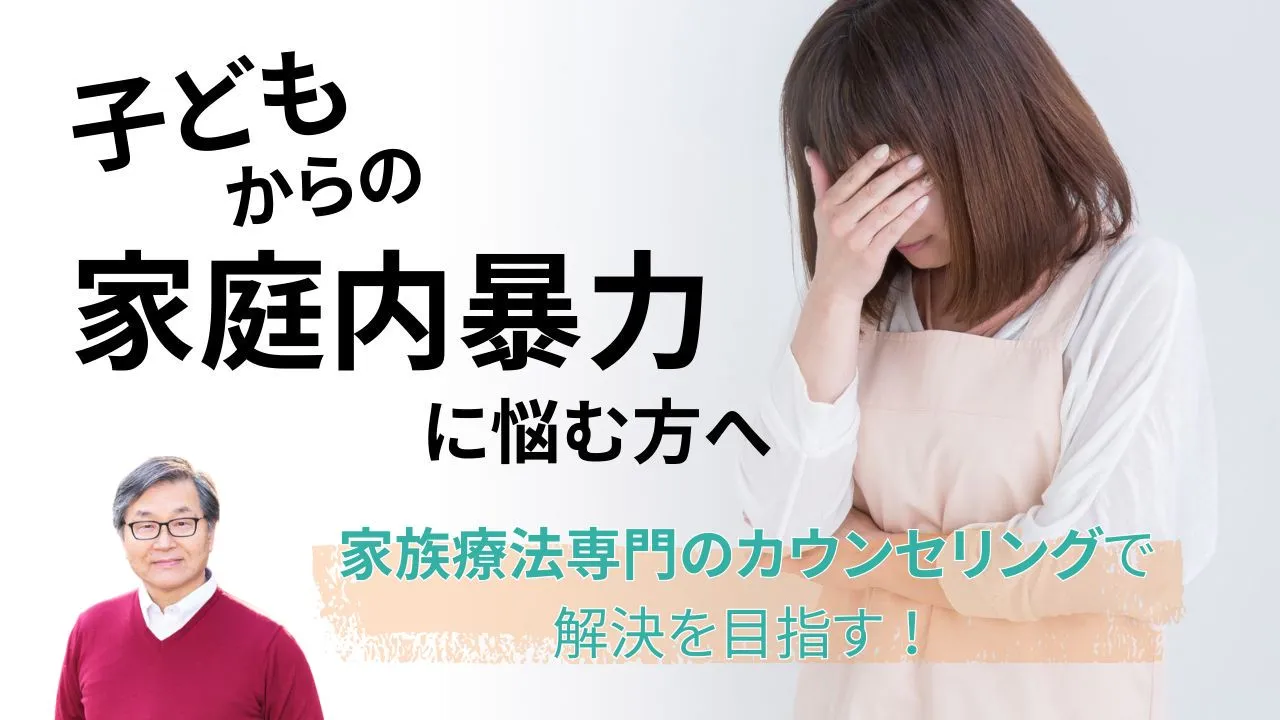
「薬を処方されて終わってしまった」
「入院を勧められた」
家庭内暴力や暴言を繰り返すお子さんの治療で、このような経験をされたご家庭は少なくありません。親子で勇気を出して治療へと踏み出したのに、期待していたようなサポートが得られず、心身ともに疲弊している方もいらっしゃるでしょう。
そんなご家庭に寄り添うのが、淀屋橋心理療法センターです。当センターでは、お子さんが来なくても、親御さんご自身を対象とした家庭内暴力・暴言に関するカウンセリングを行っています。
2025年1月14日に開催された当センターの『お子さんの暴力・暴言に悩まれている親御さん向け治療説明会』では、臨床心理士・福田俊介を講師として、親御さんを通したカウンセリングの具体的な方法や、実際に息子さんの家庭内暴力を克服された方の事例などを解説しました。
本レポートでは、治療説明会の内容の一部や、説明会に参加された方々の声などをお届けします。また、これらの情報が、苦しんでいる親御さんお一人おひとりに寄り添い、新たな解決策への一歩となることを願っています。
子どもの家庭内暴力の解決には親の協力が不可欠

家庭内暴力を解決するには、何が大切なのでしょうか。治療説明会では、お子さんが暴力に訴えないようにするために「親御さんができること」をお伝えしました。
対症療法では解決が難しい
これまで他機関に相談して、以下のような治療を提案されたご家庭も多いのではないでしょうか。
- ご本人さんのカウンセリング参加を勧める
- 投薬治療のみ
- ご本人さんの入院や親子分離を勧める
これらはなかなか効果があがりにくく、ご本人さんの参加を勧めるため、お子さんに強い負担がかかります。
また薬物治療や入院など、病気のように扱われることに心を痛める親御さんも少なくありません。
特に入院した場合は、完治して退院しないと、退院してからも「あのとき入院させたな!一生許さない!」 など、入院させたことを長期にわたって親御さんにぶつけ続けることもあります。
このような場合は、明るい未来が期待できません。では、どうすればお子さんの暴力・暴言を改善できるのでしょうか。
家族の協力で、暴力に頼らない子どもに
家庭内暴力の解決には、お子さんが自身の気持ちを言葉で表現し、親御さんとコミュニケーションすることが大切です。
多くの場合、お子さんはより良い人生を送りたいと願いながらも、自信を失い不安でいっぱいの状態です。
家庭内暴力を解決するには、お子さんの心をほぐしていかなければなりません。実は、普段見逃している些細なところに糸口があるのです。
親の精神状態がカウンセリングに影響
親御さんが精神的に不安定な場合、カウンセリングがスムーズにいかないこともあります。
親御さんのなかには、育て方やお子さんへの接し方を後悔し「自分のせいではないか」と責任を感じている方が多くいらっしゃいます。ご自身を責めるあまり、イライラしたり冷静さを欠いたりすることもあるかもしれません。
淀屋橋心理療法センターでは、「この調子だと、今は大変でも3ヶ月くらいすると暴力はゆるんでいきますよ」など、暴力の矢面に立っている親御さんを励ましながらカウンセリングを進めていきます。
親御さんの精神状態が落ち着いているときこそ、カウンセラーからのアドバイスが心に響き、治療への協力も得られやすくなります。
当センターでは、治療過程で親御さんの心の状態を常に把握しながら、適切にサポートしていきます。
家庭内暴力を起こしやすいお子さんの特徴

家庭内暴力を起こしやすいお子さんには、以下の特徴が見られます。
- 自分の性格の操縦に苦労しているしっかり 言葉で伝えるのが苦手
- 完璧主義
- 外でいい子でいようと相当無理している
このようなお子さんの多くは、物事がうまくいかないと人のせいにする場合もあります。
「お前が学校を選んだせいで、中退したんだ!」
「お前の育て方が悪かったせいで、仕事がうまくいかないんだ!」
など、特に母親への当たりが強く、家庭の中でお子さんが支配的になっている点も特徴です。
淀屋橋心理療法センターでは、お子さんの性格を徹底的に分析し、ひとり一人に合ったアドバイスをお伝えします。
たとえば、精神的に伸ばすべきところがあるなら心が成長できる働きかけを、言葉で伝えるのが苦手なら言語化を促すアドバイスを行います。完璧主義のお子さんであれば、完璧主義の度合いを少し緩められるような援助のしかたをアドバイスします。
家族療法のカウンセリング治療とは?
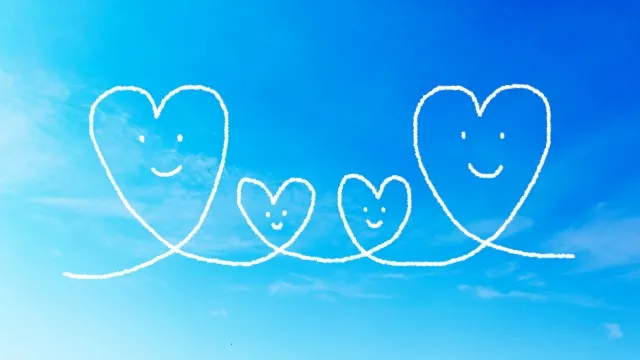
淀屋橋心理療法センターでは、独自の家族療法を行っています。治療説明会の内容から、従来の認知行動療法との違いや、淀屋橋心理療法センターのカウンセリング方針について紹介します。
子ども本人の来所不要
淀屋橋心理療法センターでは、お子さんご本人がカウンセリングに来なくても、ご家族だけで問題解決に向けて取り組むことが可能です。
臨床心理士・福田俊介によると、従来の認知行動療法はご本人さんの参加が必要とされてきました。お子さんを参加させるためには、問題を抱えているご本人さん自ら変わろうとする意欲が必要です。
しかし、家庭内暴力を繰り返すお子さんは、治療に消極的なケースが多いことも課題でした。
このため、当センターではご家族に協力いただくことによって、家庭内暴力・暴言を解決に導くカウンセリングを行っています。長年の実績とノウハウにより、お子さんの来所がなくても解決に至った治療経験が多数存在します。
親の努力の先に明るい未来がある
「親御さんのコツコツとした努力の先に、明るい未来があります」
親御さんに向けた、臨床心理士・福田俊介の言葉です。
ご本人さんと親御さんとの関係が少しずつ変わるなか、ご本人さんが成長していかれるのです。
淀屋橋心理療法センターのカウンセリングでは、お子さんが精神的に大きく成長できるようアドバイスしています。
もちろん、暴力のひどさ・危険度・親御さんの疲労度なども考慮します。
暴力に走る前のお子さんに戻すだけではなく、困難を乗り越えて、精神的に大きく成長した姿を目指しています。
家庭内暴力を治す魔法の言葉はありません
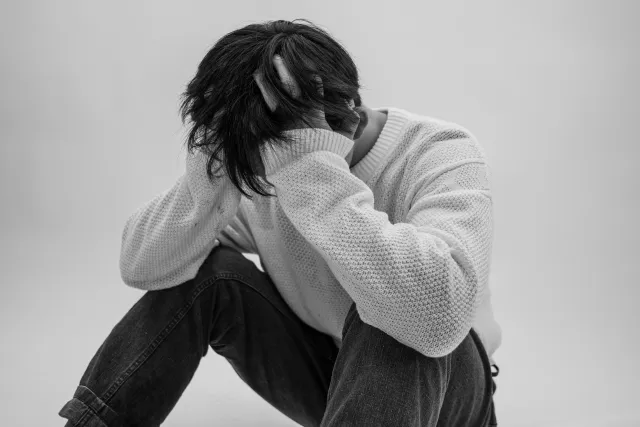
残念ながら、家庭内暴力を一瞬で治す魔法の言葉は存在しません。
しかし、ご本人さんの持ち味にぴったりの相性を合わせていくことで、会話を豊かにすることができます。淀屋橋心理療法センターのカウンセリングでは、「会話を工夫してみてください」と親御さんにアドバイスしています。
お子さんとの会話を増やす技術はたくさんありますが、ここではその一部を紹介します。
知らないふりをする
お子さんからの質問に「知らないふり」をすると、会話が広がるきっかけとなります。会話のネタは、芸能情報やスポーツ情報、アニメ・映画でも何でもかまいません。
会話の例
お子さん:「芸能人の〇〇が結婚したらしいんだけど、知ってる?」
親御さん:「へえ、そうなんだ!?知らなかった!どんな人だっけ?」
お子さんからの問いかけに、本当は知っていたとしても知らないふりをして会話を続けることが大切です。
お子さんのおかげで知れてよかった・もっと知りたいから教えてほしい、これらのニュアンスを伝えてあげてください。
小さな間違いを修正しない
2点目は、お子さんの小さな間違いを修正・訂正しないことです。以下の会話例で見ていきましょう。
お子さん:「〇〇県で震度5の地震があったらしいよ」
親御さん:「 いやそれ、震度4だよ 」
このように、小さな間違いをすぐさま修正してしまうのは危険です。なぜなら、親御さんからの修正や訂正があまりにも多い場合、お子さんは喋りたくなくなるからです。
特にまじめな性格の親御さんほど、修正や訂正をしたくなる傾向があるので、ここはぐっと我慢しましょう。
また、意見を否定することも会話が減る原因になりえます。たとえば以下の例です。
お子さん:「YouTuberの〇〇が、こんなことを言っていたんだって」
親御さん:「いや~お母さん、〇〇さんの意見は違うと思うな 」
このようなごく軽い否定でも、お子さんは話すのをやめる可能性があります。ささいな間違いや意見の食い違い程度であれば、あえて正さずに、そのままにして会話を続けてみてください。多くの場合は、その方が会話がスムーズに展開します。
家庭内暴力を解決した実際のケース
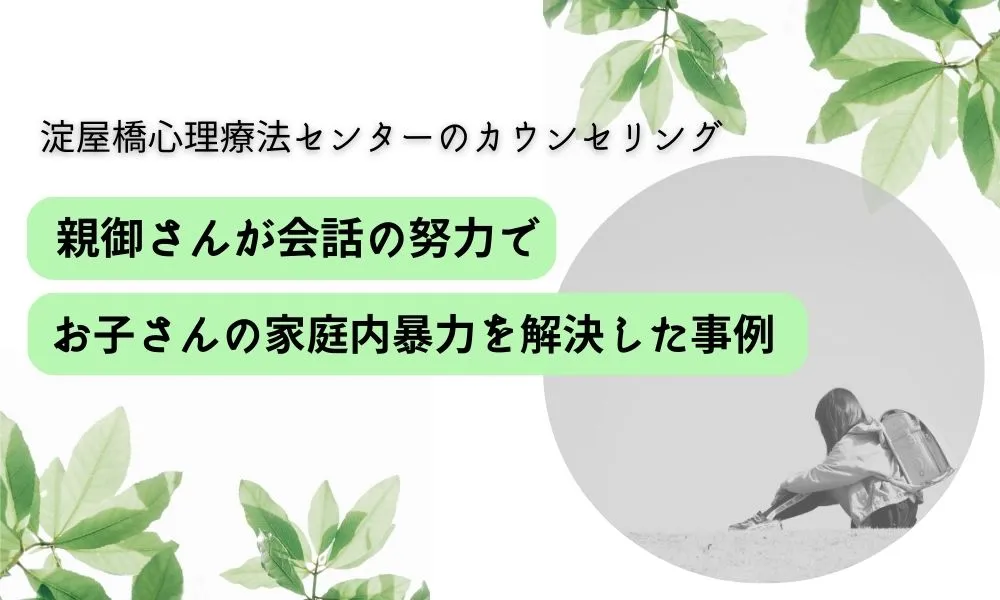
淀屋橋心理療法センターのカウンセリングに通いながら、親御さんのコツコツとした実践が実を結び、暴力・暴言の解決に至ったケースを紹介します。問題解決まで、約4ヶ月を要しました。
治療過程とともに、カウンセラーからのアドバイスの一部をご紹介するので、ご参考になさってください。
お子さんの状態とカウンセラーからのアドバイス
お子さんと親御さんの状態は以下です。
| 年齢 | 中学2年生 |
|---|---|
| 性別 | 男の子 |
| 家族構成 | 父・母・ご本人さんの3人家族 |
| お悩み | ゲーム依存と家庭内暴力 |
| 家族の状態 | お母さんは息子さんと距離をとり、ホテルで過ごすことも多い |
お子さんの性格には、
- 人目が気になる
- 完璧主義で失敗したくない
- 傷つきやすい
といった特徴があります。例えば、ご本人さんの好きなゲームでガチャがうまくいかなかった場合に、暴言を吐く・叫ぶ・殴るなどの暴力をふるうといった状態です。お母さんの精神状態も良くなく「暴力さえなくなれば…」と切に願っています。
まず、臨床心理士・福田俊介からのアドバイスは、
カウンセラーからのアドバイス
親御さんは、お子さんが機嫌のいいときの会話を大事にしましょう。
「一日中荒れていて、機嫌のいいときなんてないです」
親御さんのなかには、このように思う方も多いでしょう。しかし、家庭内暴力を繰り返すお子さんであっても、一日中機嫌が悪いというわけではありません。
たとえ一瞬でも機嫌のいい瞬間があれば、そのチャンスを上手く利用します。
カウンセリング後の変化
カウンセリングによるアドバイスを親御さんに実践してもらった結果、少しずつ変化が現れてきました。
息子さんと、電話でゲームの話が長続きするようになったそうです。
さらにお母さんの精神状態が落ち着いてきたころ、息子さんの心に変化が。
- 不機嫌な時間が短くなり、家の手伝いもするように
- 「今すぐ買ってこい!」の命令的な発言から「次のときでいいよ」のように柔らかい発言に
2週間後、荒れはするものの暴力がなくなり、ときには笑うように。さらに4週間後には「いつもゲームの話ばかりでごめん」とお母さんへ謝る発言も。
「荒れた後の気持ちの切り替えが早くなった」とお母さんも仰いました。
これらの変化はすべて、お母さんが自らカウンセリングで報告なさったことです。
「お子さんの小さな変化に気づけるご家庭は、家庭内暴力を解決できる可能性が高い」と臨床心理士・福田俊介は語っています。
荒れる波が来ても慌てない
一見良くなったように見えるころ、再び荒れる波が来ることがあります。お母さんをいたわったり、ゲームを途中で切り上げたり、自分自身で感情をコントロールできるようになっていたなか、突然、彼は荒れて、壁に穴を開けました。
しかし、お母さんは荒れる波があることをあらかじめカウンセラーから聞いていたため、精神的ダメージが少なく済んでいます。ある日突然、荒れる波が来ても、
- 慌てふためかない
- お子さんの状態には波があることを知っておくこと
これが、大きな助けになります。
その後も会話の活性化が続き、最終的には、お母さんの好きなタレントについても会話がはずむように。お子さんは、他者の好きなことに関心を寄せて、会話をふくらませるまでに成長しました。
事例が伝える「雑談」の大切さ

お子さんとの「たわいのない話=雑談」ほど大事なものはありません。親御さんが雑談に秘められた可能性を理解し、雑談からお子さんの小さな変化に気づけるかどうかで、結果は大きく変わります。
雑談を大事にしていない家庭は多い
臨床心理士・福田俊介によると、家庭内暴力が起きているご家庭では雑談を大事にしていない場合が多いようです。
大人同士の人間関係に置き換えてみるとわかりやすいでしょう。雑談が気持ちよくできると、真剣な話や自分の趣味の話などもしやすくなりますよね。
お子さんも同様です。雑談のような軽い話もできない親御さんには、自身の心の内を話そうとは思わないでしょう。
ぜひ、お子さんとたわいのない雑談ができるように、根気強くトライしてみてください。上述のケースでも、結果として「ゲーム以外の話」に花が咲くようになりました。

「中身のない話を続けた先に、中身のある話があります」
と、臨床心理士・福田俊介は語っています。
親が子どもの変化に気づく
親御さんがお子さんの小さな変化に気づけるようサポートするのもカウンセラーの腕の見せどころです。
ご紹介したケースでは、お母さんはお子さんの良いところに気づくのが上手になりました。その理由として、こう答えています。
「何度も先生から、良い変化はあったかを聞かれたから」
またお子さんと距離をとることで「客観的に見れるようになり、視野が広がった」とも答えています。これにより、お子さんの良い面に気づくのが上手になったのでしょう。
この事例から、
- お子さんの一番好きなこと(事例ではゲームの話)を話題にすること
- 話題をどれだけ言語化できるかどうか
が会話を増やすカギとなることがわかります。つまり雑談には、お子さんの可能性を引き出すちからがたくさん詰まっています。
治療説明会に参加された方々のお声
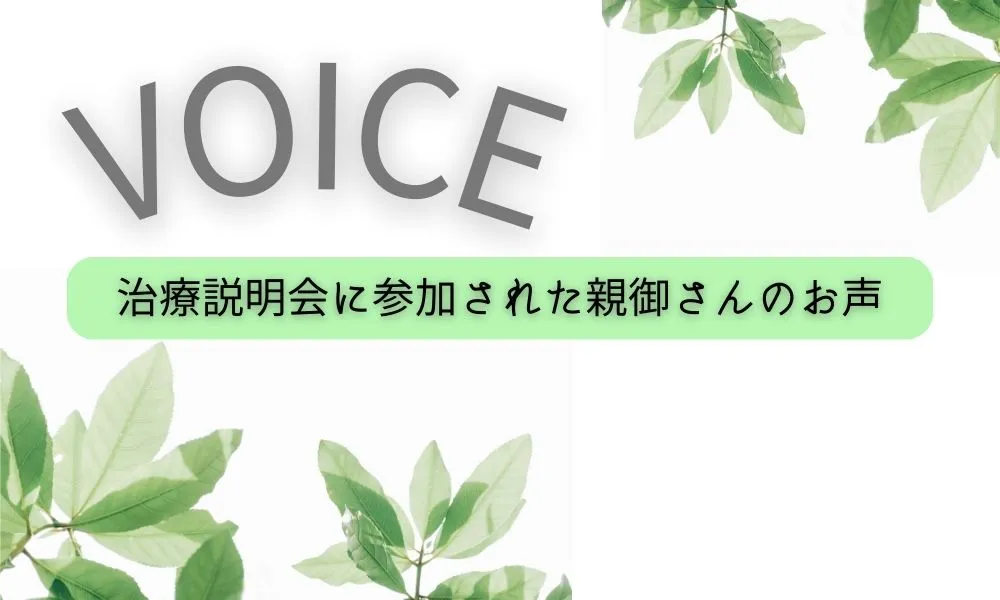
ここでは、治療説明会にご参加いただいた親御さんからのメッセージを一部ご紹介します。
子どもとのたわいのない会話を大切にしたい
- 今日の事例では、お母さんの興味あること(タレントの話)に息子さんが関心を持つようになっていて、そこに至るまでの変化が印象的でした。
- 雑談を通して、子どもの良いところを見つけたいです。
- 子どもに話しかけるタイミングが難しいけど、子どもからの質問にはズレずに答えようと思います。
- 子どもがわたしに、おすすめのYouTube動画を送ってきていたのに、スルーしていました。これからは、きちんと見て感想を伝えてあげたいです。
親の気持ちの持ち方を意識したい
- これまでは、自分がイライラしているときもあったかもしれません。子どもの話を聞くときは、落ち着いて聞いてあげたいと思います。
- 良くなってきていると思っているときに、突然悪い波が来るとかなりがっくりしてしまうけど、子どもの状態に左右されないようにしたいです。
今回の治療説明会は、筆者も一人の親として、自身の姿勢を見つめなおす機会となりました。今後はきちんと子どもの方を見て、目を合わせ、話を聞いてあげたいと強く感じました。
精神科医・福田俊一によるQ&Aコーナー
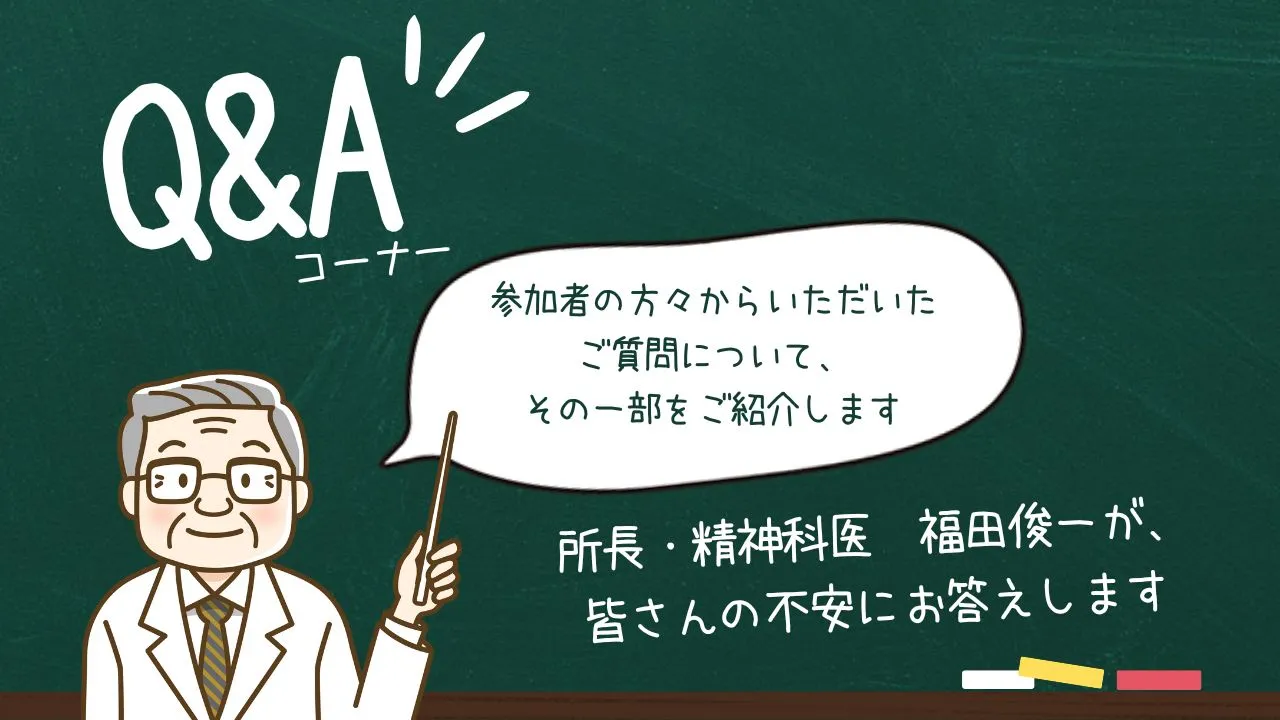
治療説明会の最後に、精神科医・福田俊一によるQ&Aコーナーを設けております。
Q&Aでは、家庭内暴力への対応だけでなく、不登校やゲーム依存症に関する質問も多く寄せられました。ここでは、その一部をご紹介いたします。
Q:家庭内暴力に加えて、ゲーム依存症ではないかと心配しています
家庭内暴力だけではなく、常にスマホやゲームを手放せず、画面を見ていないと落ち着かない状態で、ゲーム依存症ではないかと心配しています。スマホ・ゲームについて家庭内ルールを作ったものの、現在は崩壊しています。
A:興味関心をゲーム以外のことにうまく伸ばしてあげることが大切です
一度崩壊してしまったルールを立て直すことは、難しいでしょう。
お子さんの場合ですと、何か他に集中するものがなかった結果、信じられないほどの興味関心をひくものに出会ってしまった。それが、たまたまゲームであったと考えられます。
他の出来事にも関心が持てるようにうまく伸ばしてあげれば、その興味関心をゲーム以外のことへ向けられるようになるのです。我々は、会話のチャンスを見つけて、親御さんがコツコツ努力されることで、それを実現できるようガイド役をします。
Q:不登校の子どもに対する声掛けはどうしたらよいか?
学校になかなか行けていません。どのように声掛けをしたらよいでしょうか。何度も「今日はどうする?」と子どもに聞いてよいものか、とても迷っています。
A:お子さんの反応によって対応は異なります
どのような対応をするかどうか、お子さんの反応によります。
特に、家庭内暴力を繰り返すお子さんの場合は、親御さんがお子さんを避けるようになると解決しにくくなる場合が多いです。
逆に、親御さんのほうから何か言って、お子さんが避けるようになるのであれば、声掛けはやめておいたほうがよいでしょう。
Q:激しい暴力・暴言にはどう対応したらよいか?
激しい暴力・暴言の際に直面した際の対応に苦慮しています。どのように対応すればよいでしょうか。
A:お子さんを怒らせないパターンを知ることから始めましょう
その場の対応だけで暴力・暴言を止めることは難しいでしょう。比較的効果があるのは、会話をメモすることです。
- お子さんの暴力・暴言に、親御さんはどのように返事をされたか?
- その結果、お子さんがどのように発言を返したか?
以上を記録しておくことで、お子さんを怒らせないパターンが見えてくる場合があります。しかし、お子さんが根本的に成長し、暴力がなくなるためには、
- たわいのない雑談ができ、
- お子さんがとても話しやすいリズムで喋れるように、
- 自分の性格をうまく乗りこなせるように、
成長する糸口を見つけてあげることです。余裕のないなか、コツコツ対応を工夫し、解決に至るには、プロのガイド役がいないと難しいかもしれません。
淀屋橋心理療法センターまで相談していただければ、親御さんとの雑談を通して、精神的に落ち着いていけるよう、解決の糸口までガイドしていきます。
Q:家庭内暴力・暴言を母親にばかり向けてくるのは、なぜか?
暴力や暴言を、母親にばかり向けてくるのはなぜでしょうか。母親への「恨み」からでしょうか。
A:恨みもあるかもしれませんが、母親とは距離が近いからでしょう
恨みがあったとしても、母親とは普段から距離が近く、当たりが強くなりがちです。父親に対しては警戒心や力負けを感じることがあるため、母親へ気持ちが向きやすいと考えられます。
家庭内暴力をしてしまう子どもは、内なるエネルギーを持て余し、自分にも他人にも否定的な感情を抱いている場合が多いです。
ご本人さんが、自分の良いところに目を向けられるようになることが、解決への糸口になります。そのためには、親御さんはコツコツと対応を工夫し続けることが求められます。
お子さんが自分自身を認め、好きになれるまで、時間がかかるかもしれません。親御さんにとっても、けっして簡単な道のりではないでしょう。それでも諦めずにお子さんと向き合おうとする親御さんを、より良い方向にガイドしていくのが、我々の役割です。
家庭内暴力はおひとりで悩まず専門家に助けを求めることが大切

家庭内暴力は、お子さんの性格を深く理解し、お子さん自身が上手にその性格をうまく乗りこなせるようになることが肝心です。
淀屋橋心理療法センターの家族療法に基づいたカウンセリングでは、親御さんが、お子さんの精神面の成長を促すためのコツをつかんでいただけるよう、ガイドしていきます。
不定期に治療説明会も開催しています。お子さんからの暴力や暴言にお一人で悩まず、まずはお気軽にお問合せください。
お子さんが人生の壁にぶつかったときに、暴力を振るうのではなく、自分自身と向き合い、どのように乗り越えれば良いのかを考える力を身に着けられる力を育んでいきましょう。